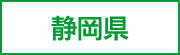◯内田隆典
通告に従いまして質問します。
最初にPFAS問題についてであります。
発がん性物質が指摘されている有機フッ素化合物──PFASによる環境汚染が全国的にも大きな問題になりました。当初は、このPFASの広がりは、中心は沖縄や東京多摩など米軍や自衛隊基地周辺での環境汚染でありましたけれども、私どもが住む清水地区で、この問題が大きな問題になるとは私は考えてもいませんでした。私は2月議会でもこの問題を取上げましたけれども、一言で言って、原因者であります三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社の対応は不十分だと感じております。
この間、静岡市も周辺井戸を調査して、国の暫定指針値を大幅に超えるという値が出ましたから、関係者に対して飲料水の使用をやめるよう連絡しているところであります。三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社も遮水壁等の対応を検討してきましたけれども、現地の地層の特殊性から、工法の検討を延期したと報道されているところであります。
そこで、当該企業と地元自治会と静岡市で組織している三者連絡会の活動状況を伺いたいと思います。
次に、当該企業と静岡市のこれまでPFAS対策の進捗状況はどうなっているのか。この内容がなかなか明らかにされておりません。そういう中で、今年5月の新聞報道によりますと、Aホールディングスという会社が活性炭によるろ過よりも大量処理可能な除去装置を実用化したという報道がされておりました。これがどういう形で三保地域のポンプ場を含めて処理されるのか、具体的にはされておりませんけれども、当局は三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社工場内外の汚染状況がどれくらいになっているのか、その把握はされているのか、私はこのことが気になるわけであります。そして、汚染されているこの状況を会社は具体的にいつまでに処理しようとしているのか、そのことについてもなかなかはっきりしないわけであります。市が当該企業に対し、PFAS対策としてこれまでどのような対応をしてきたのか、その進捗状況について伺いたいと思います。
それから、住民説明会について改めて伺いたいと思います。この間の環境局長の答弁では、そういう住民説明を求める話はなかなかないわけで、説明会を開催することもないだろうという、これは会社も失礼な話ですけれども、当局もこの問題について状況をきちんと把握していないと私は思っております。
そこで、原因者の当該企業に対して、住民説明会を開催すべきと私は思っておりますが、当局の認識について改めて伺いたいと思います。
それから、産業廃棄物について関連して伺いたいと思いますけれども、PFASの環境汚染は全国的に問題になっており、岡山県の吉備中央町では浄水場の水から国の暫定目標値の28倍を超えるPFASが検出されたとのことです。原因は、取水源上流に置かれた使用済み活性炭だと報道されておりました。
そこで伺いますけれども、三保にある当該企業の工場から排出された産業廃棄物は適正に処理されていると思いますけれども、静岡市は廃棄物についてどのように確認されているのか、伺いたいと思います。
次に、学校給食について伺いたいと思います。
清水地区では、ほとんどの小学校がこれまで自校方式の学校給食を提供してまいりました。中学校については、東部学校給食センターからほとんど提供されております。しかし、東部学校給食センターは、開設が昭和48年5月ということで、老朽化が進んでおります。小学校についても、建て替えの時期を迎えているところがあろうかと思います。
こうした中で、静岡市が清水区船越地区に進めておりました、県が準備しております畑総の一部に1万食の給食センターの建設計画を発表しておりましたけれども、この建設計画を見直すという報道もされております。
そこで、清水区の学校給食の整備方針、見直しの経過と判断はどのようなものだったのか、伺いたいと思います。
2点目は、整備方針の見直しに伴う今後の学校給食の供給体制でありますけれども、教育局長は、昨年2月の我が会派の杉本議員の質問に対して、このように答弁しております。
新しい学校給食センターの整備に当たっては、児童生徒のさらなる減少や物価及び燃料費の高騰、調理員の確保が難しい状況などを考慮し、より効率的で社会の変化に柔軟に対応できる施設とする必要があると。従来の運営や調理、提供方法にとらわれず、施設の効率的運用を図り、学校給食以外の事業への活用など、これまで以上に民間活力の導入を視野に入れ、検討していくと答えておりました。
整備方針の見直しに伴い、具体的に、今後、学校給食はどのような体制で提供していこうと考えているのか、伺いたいと思います。
次に、清水区の学校給食における単独調理場の親子方式についてであります。静岡市が2029年度から清水区の大半の小学校17校で自校方式を取りやめ、1万食を一括の調理方式で提供するという方針を打ち出しまして、清水・学校給食を考える会から、昨年6月議会に自校式給食の継続を求める請願が提出されました。
今、船越地区の1万食規模の給食センターの見直しがされており、東部給食センターも老朽化しているという時期でありますから、新しい給食センターを改めて造る方向にあろうかと思います。そのときに、清水地区で親子方式を含めた検討を進めたらどうかと思いますが、考え方について伺いたいと思います。
次に、清水庁舎について伺いたいと思います。
清水庁舎は昭和58年に建設されています。平成23年3月に発生した東日本大震災による被害状況を受け、現庁舎が津波浸水等の大規模災害を受けた場合、業務継続に与える影響等について、この間、調査を行ってまいりました。
平成29年には、学識委員や市民からの公募委員を含めた、建設検討委員会を設置し、検討や市民アンケート等を行い、この間、新清水庁舎建設基本構想を立ててきました。こうした経過の中、難波市長は今年3月28日の記者会見で、清水庁舎について、現地改修費とJR清水駅周辺への新築移転費を比較した結果、現庁舎の一部機能を既存施設に移転する新築案が最も安価になると明らかにしていました。
今後、立地場所の詳細を詰めて、新築案の積算精度を高め、本年度末頃に最終案を決定することになっているようであります。
そこで、令和7年度に決定する予定の整備方針について、現在、どのような検討が行われているのか、伺いたいと思います。
次に、これまでの経過を含め、検討委員会は設置せず、内部で整理し、市としての最終案を示すとのことでありますけれども、2022年の検討委員会は、学識委員・公募委員を含め、議論やパブコメ等を行い、案を示しています。最終案の決定までにどのような過程を想定しているのか伺って、1回目とします。
◯市長(難波喬司)
私からは、清水区の学校給食センターの整備方針の見直しに伴う3つの質問について、一括してお答えします。
2022年12月に清水の船越地区に清水区を配食エリアとする1万食規模の学校給食センターを整備する方針を決定しました。しかし、市長就任後の当初に、この方針の説明を受け、即座に問題があると判断しました。児童生徒数の減少が見込まれることから、将来の児童生徒数の推計を基に、葵区、駿河区を含めた市全体の学校給食の提供の在り方を見直す必要があると考えたためです。その後、学校給食センターや学校内での調理状況、配送システムの現場を見に行きました。その結果、現在の給食供給システムには抜本的な改善が可能であると確信いたしました。
見直しの内容としては、給食供給全体量としては、新センターを設置しなくても既存の他の給食センターを含めた供給体制の見直しで供給可能になると考えています。1万食規模のセンターの新設は、確実に過剰投資になります。
一方で、総供給量は足りていても、配送時間等の問題で学校に適切な時間内に届かないという問題があります。したがって、総供給量だけの問題ではなくて、配送も含めた供給システムとしての給食提供の在り方を考える必要があります。供給システムとしては、学校給食の供給体制は、共同調理場方式である従来の学校給食センター、各学校に設置された単独調理場、そして単独調理場を活用した、いわゆる親子方式などがあります。そして、独自の物流システムによって学校に届くようになっています。もちろん、単独調理場ではその場ですぐ教室に届くわけです。
これからの30年の供給体制を考える際には、これまでの延長上の供給システムにとらわれずに考えるべきです。今、30年と申しましたのは、新しいセンターを造るとすれば、それは30年は使うということになると思いますので、これから新しい給食センターを仮に造るというのであれば、そういう30年後まで含めて考えていく必要があると思います。
そして、社会全体の動きとして、食の供給システムは大きく変わってきていますし、今後、さらに変化、進化していくことが予想されます。これからの学校給食の在り方を考える際には、単に学校給食だけで考えるのではなくて、持続可能な食の生産、流通、加工、消費の全体システムという農と食の未来を考えた上で、この中でどういう学校給食供給システムにするかを考える必要があります。
現在、今年2月に立ち上げた静岡食と農システムプロジェクトチームにおいて、今後のスケジュールを含め検討しています。本年度中には、基本的な考え方などを示していきたいと考えています。
単独調理、あるいは親子方式についてですが、まず、単独調理かセンター方式かという二者択一、あるいはどちらが優れているかというような問題ではないと私は思っています。単独調理や親子方式にも利点はあります。しかし、今のやり方のままの人手のかかる方式では、持続可能性は低いと言わざるを得ません。単独調理方式の利点を生かしながら、食と農の全体供給システムを活用した、少ない人数でおいしい給食を提供するという方法もあると考えております。すなわち、単独調理方式の部分の一部は残しながら、全体でうまく補完した、よりよい給食提供体制というのがあると思います。そういったことも含めて、総合的な点からプロジェクトチームで検討した結果を今年度中には出し、基本的な考え方を出したいと思っております。
その他の質問については、局長より答弁いたします。
◯環境局長(大村 博)
PFASに関する4点の質問にお答えします。
最初に、三者連絡会の活動状況についてですが、三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社と三保地区連合自治会、静岡市による三者連絡会は、同社清水工場の周辺におけるPFASへの対応について、情報を共有し、三者の緊密な連携により適切な対応を検討することを目的として設置されたもので、これまでに15回開催しております。直近では、本年5月14日に開催しました。同社からは、清水工場周辺の雨水排水管の補修等の状況、三保雨水ポンプ場における中型活性炭塔の稼働状況及び大型浄化設備の検討状況、同社清水工場敷地内の地下水浄化及び土壌対策の進捗について報告がありました。静岡市からは、地下水等のモニタリング調査結果を報告し、自治会からはそれぞれの報告に対して御意見をいただきました。
これらに加え、今後の工場敷地内の地下水拡散防止対策として、対策井戸の設置方針について説明があり、対策の有効性について意見交換を行いました。
引き続き、同社、地元自治会と連携し、本件に対する適切な対応を検討していきます。
次に、PFAS対策の進捗についてお答えします。
1点目として、三保雨水ポンプ場への対策ですが、これまでに同社では、三保雨水ポンプ場へ接続する雨水排水管に工場敷地内からPFASを含む地下水が流入していることが考えられたため、工場敷地周辺の雨水排水管の調査及び補修を実施してきました。また、同ポンプ場排水の浄化対策として、1日当たり処理水量が720立方メートルの中型活性炭塔を設置しました。処理後のPFAS濃度は検出下限値未満まで低減していることを市も確認しております。
今後の対策として、1日当たりの処理水量を増やすため、雨水ポンプ場への大型浄化設備設置を計画しています。現在、同社が適正な処理能力及び処理方式の採用に向けた検討を行っています。
2点目として、工場敷地内の対策についてですが、これまでに同社では、工場敷地内地下水の浄化のための中型活性炭塔を設置するとともに、工場敷地内土壌については、濃度が高いエリアの土壌の入替え及び封じ込めの対策を実施しています。これらに加え、工場内から周辺に地下水が拡散することを防止する対策として、本年5月の三者連絡会において、PFASを含む地下水をくみ上げて浄化する揚水井戸と、PFASを含まない清浄な水を地下に注入する注水井戸の組合せによる対策井戸の設置方針について説明がありました。
この対策井戸は、PFASの拡散防止対策として遮水壁と同等の効果があるものと期待されます。静岡市では、水質調査を継続するとともに、早期に大型浄化設備及び対策井戸の設置が実現されるよう要請していきます。
続いて、住民説明会の開催に関する市の認識についてですが、令和7年2月定例会においてもお答えしたとおり、企業側の責任による住民説明会の開催につきましては、同社が適切に判断されるものと考えております。
なお、同社と地元自治会、静岡市で組織する三者連絡会においては、住民説明会を開催してほしいとの意見はありません。
最後に、産業廃棄物の適正処理の確認についてですが、同社は清水工場の産業廃棄物発生量が年間1,000トン以上であることから、廃棄物処理法で規定する多量排出事業者として、毎年度、産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が義務づけられております。静岡市は、同社清水工場から排出される産業廃棄物の適正処理について、これらの報告書及び公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターから取得できる電子マニフェスト情報により確認するとともに、定期的に立入調査を実施し、保管状況及び委託書類等の確認を行っています。
直近の令和5年度の立入調査では、産業廃棄物が周辺環境へ飛散、流出、地下浸透しないよう保管基準を遵守していることを確認しております。
今後も引き続き、産業廃棄物の適正処理について指導を徹底していきます。
◯財政局長(野村一正)
清水庁舎への対応についての2つの質問にお答えします。
まず、令和7年度に決定する整備方針について、現在はどのような検討を行っているのかについてですが、令和6年度の検討では、使用年数を40年とした制震補強の現地改修案と、仮に移転新築した場合の新築案について費用を算出しました。しかし、この時点の新築案は、近年建て替えを行った近隣施設の平米単価を基に費用を算出したため、改修案に比べ積算精度が低かったことから、改修案と新築案に費用面で明確な優劣をつけることができませんでした。
このため、費用面での正確な比較検討もできるよう、現在、新築案の積算精度を高めるべく、立地場所の選定、その敷地での法令整備、必要な建物規模や配置、構造種別などの詳細な条件整備の検討を行っているところです。
次に、最終案の決定までにどのような過程を想定しているのかについてですが、令和4年度の清水庁舎整備検討委員会においては、庁舎の改修案と新築案の比較検討に必要な事業の実現性、コスト、アセットマネジメントに加え、整備中の行政サービスへの影響、災害時の防災拠点としての機能の確保、清水都心地区のまちづくり方針との整合性など、11の評価項目により比較検討しました。これらの評価項目は、いずれも必要な事前修正を加えることで、令和7年度の整備方針の検討に十分使用できるものです。そのため、今後は市の内部で検討内容を詰めた上で、様々な方の意見を個別に伺い、静岡市としての最適案を決定する予定です。
また、調査整備については、令和4年度清水庁舎整備の方向(改修)に基づき、現在検討を進めておりますが、整備方針を新築案に変更する場合には、庁内協議の上、最終案を決定することとなります。
なお、市民意見の聴取については、令和6年9月議会で答弁したとおり、様々な機会を通じて整備方針の最終案を市民の皆様に丁寧に説明するとともに、意見聴取の機会を設けたいと考えております。
◯内田隆典
PFASですが、いろいろ説明していただきましたけれども、この問題がどういう形でいつまでに処理されるのかということが、私は今の時点でも明確になっていないと思うんです。ここは、行政として当該企業を正していく必要があるということを私は言っておきたいと思います。
それから、住民説明会の問題は、私は前回も質問させていただいたんですけれども、言っていることは分かります。当該企業が住民説明会をやるのは当然なんですけれども、やらないということが問題になっているんです。それと、三者連絡会をせっかくつくっているわけで、ここの機能を生かしてどう会社に伝えるかというのも、事務的な役割を果たしている静岡市の1つの役割なんです。環境局長は説明会を申し入れないと私の質問に前回も答えているんですけれども、このことは三者連絡会で、本当にあるのかないのか緊密に確かめてもらいたい。あるんです。申入れがされている。三者連絡会があるんだから、状況を本当に共有して、やっぱり重要な環境問題ですから、三者連絡会の連絡をもう少し密にしていただきたいと思います。
前回もいろいろ質問したんですが、調査費用の考え方について、原因者がはっきりしているんだから、調査費用を請求したらどうだと質問したら、残念ながら法的根拠がないから、それはできないということになったわけです。監査請求から裁判があって、6月19日には第1回口頭弁論が始まったと。これに対応するのは市の職員も時間的になかなか大変だと思うんです。だから、私は質問したときに、法的根拠とか何とかじゃなくて、原因者がはっきりしていなきゃあれですけれども、原因者がはっきりしているんだから、行政側が支払いいただけるんですか、ないですかって言ってみればよかった。会社が、いや、それはできませんよと言えば、それで済んだわけでしょう。住民監査請求も起こらないし、訴訟も起こらなかったと私は思っているんです。そういう点では、私は静岡市の対応がうまくなかったと思っているんです。
それで、こういう状況を招いたわけですけれども、このことをどのように受け止めているのか、認識を伺いたいと思います。
それから、学校給食の問題でも市長からいろいろ説明をいただきまして、そういう状況になるのかなということは分かりました。それで、質問が1点あるんですけれども、学校給食の無償化について、私は前にも質問させていただきました。そのとき、市長はこれは国が実施するのが筋だと答弁していただいたと思うんです。そのとおりだと思います。基本的には教育費は無償化となっているわけですから、学校給食についても国がやるということが筋だと思うんですけれども、小学校の給食費については、いよいよ来年度から無償化という流れが出てきてまいりました。
この問題についての文科省の資料を調べてみましたら、令和5年9月の段階で無償化している722の自治体の中で、9割の652の自治体が無償化の目的として子育て支援、少子化対策を上げているということなんです。20ある政令市の中で、残念ながら、今、無償化をやっているのは大阪市だけなんですけれども、全国的に流れは広がってきていると思うんです。
そういう点で、来年度から小学校は全国でやるわけですけれども、その間、中学校については、静岡市が独自に無償化の検討に入ったらどうかと思います。その点、静岡市はどのように考えているのか、伺いたいと思います。
それから、清水庁舎についても意見聴取を含めて、今、答弁いただきましたけれども、そういう流れを取って、これから清水庁舎の検討に、年度内に結論を出すのかであります。それで、今後は改修案になるのか新築案になるのか、具体的な検討に入っていくわけですけれども、私が気になるのは、現清水庁舎はまだまだ十分使えるんじゃないかということ。それから、前の市長時代には、清水駅東口に移転しようという流れが強まってきましたけれども、そういう流れの中、ここは津波浸水想定区域だよと。そこを考慮しないで活性化、活性化って進めるのは、ちょっとうまくないんじゃないかと住民投票にまで発展したわけです。今でもそういう考え方はきちんと持って検討に入る必要があると思うんです。新築案か改修案のどちらになるか分かりませんけれども、場所を選定する場合には、津波浸水想定区域外というところも検討に入れながら、この問題を議論して、結論を出していく必要があると私は思いますけれども、その点についての考え方を伺いたいと思います。
◯環境局長(大村 博)
PFASに関する住民監査請求及び住民訴訟を受けての静岡市の考え方についてですが、本年2月20日に静岡市監査委員事務局に提出された住民監査請求は、静岡市が実施したPFASの調査費用について、原因者企業に対する損害賠償金の督促を怠っているので、損害賠償金の支払いを督促するなどの措置を講ずるべきことを求める請求でした。静岡市監査委員による決定では、自治体の責務としてPFAS調査を実施したものであり、静岡市が調査費用を負担することは当然のことであるため、調査費用の支出は損害であるとはいえない。そのため、当該監査請求には債権とすべき損害がなく、請求すべき理由がないとして、3月28日に当該監査請求を棄却し、4月1日に請求人に通知されました。
静岡市監査委員の決定を受け、4月24日に住民訴訟が提訴されましたが、原告は住民監査請求と同様の主張をしています。静岡市としては、PFASに関する調査は河川等の公共用水域の常時監視業務の一環として、市の責務として実施した調査であるとの認識はこれまでと変わるものではなく、裁判においても引き続き、これまでの認識による主張を行っていきます。
◯教育局長(増田浩一)
学校給食費の無償化について、どのように考えるのかについてですが、令和5年11月の定例会以降、複数回答弁しているとおり、学校給食費の無償化については、自治体間の競争によるのではなく、全国一律の取組とすることが望ましいため、継続して国に対し、財政支援を要望しています。現在、国において令和8年度から小学校の給食費を無償化する動きがあり、その動向を注視しているところです。
また、中学校の給食費についても無償化するよう、引き続き国へ要望していきます。
◯財政局長(野村一正)
清水庁舎への対応について、建築場所は津波浸水想定区域外も検討すべきではないかについてですが、2018年3月に策定した新清水庁舎建設基本構想を踏まえ、清水庁舎を新築する際には、公共交通が利用しやすく、商店街や公共施設などが集積する清水駅周辺への建設が最適であると判断しています。
◯内田隆典
PFASについてですけれども、環境局長は、市の責務でやったと。これは分かるんです。ただ、裁判も同じ主張を繰り返して、行政側はそういう主張をするしかないと思うんですけれども、私が質問したのは、そういうことじゃなくて、原因者がはっきりしているんだから、当初にこれを申入れていたら、こういう事態にはならなかったんですよと。主張は主張で分かるんです。だから、今後は法律が粗いからということで、今後あまりうまくない結果が出てくるんじゃないかと私は危惧しているんです。
我が党の国会議員が、PFASについていろいろ調査しているんですけれども、2019年から2022年までの4年分で、指針値50ナノグラムを超えるPFASが検出された測定地点は、20都道府県で250か所に上るそうであります。汚染源を突き止めるのはなかなか難しいということでありますけれども、国がなかなか動かず、行政側も大変だということも分かります。ただ、法律がなく、国が動かないということだけじゃなくて、調べてみましたら、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律──化審法というのがあるそうですけれども、これを見ますと、経産大臣、厚労大臣、環境大臣が企業に対して化学物質の取扱いに関する報告を求めることができることになっていると。これは、立入検査や措置命令もできることになっているそうです。皆さんに言っているわけじゃないですよ、環境局長に言っているわけ。国の動きが悪いというのは、市長に言っているわけじゃないんですよ。もう本当に情けないことですよ。こういう法律があるんだったら、国に要請しながら、地域住民の環境、暮らし、安全を守ることができるんじゃないかと思うんです。それで言っているんです。
よく、市長は言うじゃないですか。市長が職員にいろいろ求めて、いやできないと言われると、できないと言うなと。法律は変えられないけれども、条例や要綱は変えられると。だとすると、私は、行政は中身で前に進んで、住民の目線で見ていけばできるんじゃないか。さっき言ったのは例えであって、法規制がないからなかなか大変だじゃなくて、市長がよく言うようにこういう形でやっていけば、そういう立場に立てば、この問題にも法律はあるし、ないとしてもやっぱり動かしていくことができるんじゃないかという一例なんです。そういう点は、原因者がもっと前に出てきて、きちんとやってくれればこういうことにはならないと思うんですけれども、ぜひ、そういうことも研究しながらやっていただければありがたいなということです。
それから、学校給食の問題で国に要望していると。国がやるのが筋だというのは私も分かります。さっき答弁していただいたように、近いうちに、小学校は国が対応するということですけれども、中学校をどうするかということで今、大阪市だけが政令市の中でやっているということですけれども、福岡市長が、昨年12月定例会で少し踏み込んで、給食費の負担軽減にとどまらず、無償化というところに踏み込んだ発言をしたそうです。それで、京都市会も去年11月議会で全会一致で決議を取ったそうです。だから、だんだん小さい市町村だけでなくて、政令市の中でもそういう動きが出てきているということです。こういう動きを、議会が決議すればいいんです。何らかの形でしましょうよ。そういう動きがあるということを言って、静岡市も検討に入っていただきたいということを言って、質問を終わります。