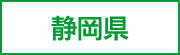〇杉本 護
日本共産党の杉本 護です。
通告に従って、質問をします。少し喉を傷めていまして聞きづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
今回の質問のテーマは2つ。1つは人口減少対策について、いま一つは小規模修繕事業者登録制度について聞いていきます。
最初に、大項目の1つ目の人口減少対策についてです。
まず、静岡市の人口減少の要因分析と対策に向けた調査研究最終報告書についてお聞きをします。
詳細については、資料として準備しましたから、ぜひ要約版を御覧ください。
この報告書は市政変革研究会の人口減少対策分科会がまとめたものです。
本市の特徴として、人口減少の要因とされる婚姻率、出生率、そして若者・女性の人口流出の指標が大都市と比べ際立って悪い状況にあるとして、根底にある原因を明らかにするために、静岡市版の出生動向基本調査、転出入アンケート調査、雇用及び就業環境に係る実態・ニーズ調査の3つの調査を行っています。
静岡市版出生動向基本調査の結果では、本市の女性が考える結婚の障害のうち、経済的な不安が全国よりも強い傾向にあり、理想の数の子供を持たない理由では、子育てや教育にお金がかかり過ぎることなどの割合が高いとされています。こうした調査を踏まえて、分科会では人口減少対策として5つの方向性を示しています。結婚・出産環境の改善、子育て・教育環境の改善、可処分所得の増加、仕事の充実、そして住まいの充実の5つです。
今後、本市は、この分科会の最終報告書の内容をさらに検討し、市の施策へと具体化が図られていくと考えます。私は、どれもが大切な視点であり、一つ一つ確実に取り組んでいくことが重要と考えます。
そこで、お聞きします。
最終報告書では、結婚・出産環境の改善分野と子育て・教育環境の改善分野の対策の方向性で、経済的支援について取上げています。経済的支援はこれら2つの分野で特に重要であると考えますが、静岡市はどのように考えているのか、お願いします。
次に、大項目の2つ目、小規模修繕事業者登録制度についてお聞きします。
市内の建設業者は、本市のインフラ整備、個人住宅や公共施設の建設、修繕、災害時の迅速な復旧・復興などに重要な役割を担っています。全国的にも建設業者は減少の傾向にあり、頻発する豪雨災害や地震などの災害への対応も厳しくなっています。地震によって屋根が破損しても復旧が進まず、何か月もブルーシートがかけられたままの状況を皆さんも見たことがあると思います。
本市の建設業者も、全国と同様に年々減少する傾向にあり、大きな問題と考えています。昨年の11月議会での私の質問に対して当局は、本市の建設事業所数は2012年から2021年の10年間で約12%減少していて、建設業者の減少は市民生活に多大な影響を及ぼすとして、建設業の担い手確保、育成に取り組んでいる。そして、市内の中小建設業者の受注機会の確保に努め、小規模修繕においては2023年度、全体の約98%が市内業者に優先的に発注しているとの答弁がありました。
ただ、中小建設業者には従業員が数十人から100人を超える事業者もあれば、一人親方のような事業者もいます。
そこで、お聞きをします。
市の100万円以下の小規模修繕を受注している事業者で、建設工事の入札参加資格がある事業者とない事業者の受注割合と金額はどうなっているのか、これをお聞きして1回目の質問とします。
◯総合政策局長(岡山卓史)
結婚・出産環境の改善分野と子育て・教育環境の改善分野における経済的支援に関する静岡市の考え方についてですが、静岡市としても経済的支援は重要と考えており、結婚・出産環境の改善においては、令和6年度から、さきの杉山議員の質問にありました不妊治療費助成を開始するとともに、結婚新生活支援を拡充し、子育て・教育環境の改善においては、令和5年度から認可保育施設の保育料について第2子以降の無償化を開始するなど、様々な取組を既に実施しております。
このほか経済的支援による取組だけでなく、急病時における安心預かり保育や屋内型の子供の遊び場の設置・運営など、サービスを提供する取組を充実させることも重要と認識しています。
◯財政局長(野村一正)
100万円以下の小規模修繕において、建設工事の入札参加資格である事業者と資格のない事業者の受注割合と金額についてですが、令和5年度の一般会計で静岡市が発注した100万円以下の小規模修繕は合計7,411件で、金額は27億円余でした。
そのうち建設工事の入札参加資格のある事業者への発注は6,389件、割合としては86%、金額は25億円余で、資格のない事業者への発注は1,022件、割合は14%、金額は2億6,000万円余でした。
◯杉本 護
人口減少対策について質問を続けていきたいと思います。
先ほど答弁で、市は様々な子育て支援や教育支援、暮らしの応援を行っているのは分かりますが、アンケートの結果は、それでも市民の立場からすればまだまだ支援が足りない、さらなる経済的支援を求める傾向が強い、これが今の静岡市の特徴です。この市民の思いをしっかりと受け止めて対策を考える必要があると思います。
日本共産党静岡市議団は、さきの市議選で、物価高騰対策として、また人口減少対策にもつながる子育て支援として、今はアリーナ建設より学校給食費の無償化、子供の医療費、通院費の無償化、そして保育料第1子からの無償化、この3つのゼロを公約として訴え、市民からも期待の声が寄せられました。
今回はその中の2つの点についてお聞きをします。
まず、子供の医療費、通院費の無償化についてです。
市の考えを調べている中で、ホームページに寄せられた市政への御意見、御提案の回答というのがありました。その中で1歳以降の通院に係る500円の自己負担を無償にしてください、このような市民の声に対する回答として、市は地域医療の問題として取上げて、次のように回答しています。広く市民の健康を守る観点からも、必要な方が必要なときに適切な医療を受けられる環境は維持される必要があります。この回答は何を言おうとしているのでしょうか。
そこで、お聞きします。
私は、この回答からは、子供の医療費の無償化により適切な医療が受けられなくなると捉えられますが、そのような事実があるのか、お答えください。
◯こども未来局長(萩原祥古)
広く市民の健康を守る観点から、必要な方が必要なときに適切な医療が受けられる環境は維持される必要があります。そのため、静岡市では、子ども医療費を無償化した場合、安易な受診が増えることによる影響を懸念して、1歳以上の児童は通院1回につき500円を負担していただくこととしています。
なお、静岡市は子ども医療費の無償化を実施していないため、適切な医療が受けられなくなるような事実の有無については把握していませんが、無償化を既に実施している近隣市町に確認したところ、無償化によって、医療が必要な方が適切に医療を受けられなくなるようなことはないとのことでした。
◯杉本 護
私も調べました。やはり今の答弁のように、医療が受けられなくなるような影響はない、このことを私も確認しています。市民の不安をあおるようなこうした記述は直ちに訂正していただきたいと要望しておきます。
また、無償化によるあらゆる影響を考慮するのは当然ですが、私はなぜか市はマイナスの面ばかりを考えているように感じています。市民生活へのプラスの面を考えることはできないのでしょうか。
子ども医療費の無償化は、治療、診療を受けられずに亡くなる子供を救うために、1961年、岩手県の和賀郡沢内村で、1歳未満の乳児を対象に、国民健康保険に係る自己負担分の支給を実施したことから始まっています。今では子育て支援、少子化対策の事業としても全国に広がり、2024年4月1日現在で1,741市区町村の中で、入院費の無償は1,358自治体、通院費の無償は1,266自治体まで増えています。
そこでお聞きするんですが、全国で子供の医療費の無償化が進んでいる状況について、どのように考えているでしょうか、お願いします。
◯こども未来局長(萩原祥古)
現在、静岡県内35市町のうち、子ども医療費の自己負担があるのは静岡市を含め4市のみであり、静岡市は県内の他の市町に比べ子ども医療費の負担が大きい状況です。
静岡市としては、子育て世帯の経済的支援は重要であると考えており、保護者からのニーズの高い子ども医療費の制度拡充等について検討を行い、早急に結論を出します。
◯杉本 護
久々に前向きな答弁をいただいた気がします。この間、この本会議でも子ども医療費無償化を何度も求めてきましたが、その都度、全国的な課題は国に統一的な助成制度の創設を要望していく回答ばかりでした。ようやく市民の声が届いたとの感じがしています。
局長が答弁したとおり、子ども医療費の無償化で県内を見れば、入院は全市町が無料です。そして、通院も無償化していないのは静岡市と浜松市、富士市と裾野市の4市です。裾野市は本年度中に無償化の方針です。これでは通院費を無償化していない本市は、近隣市町と比べて負担が重い状況となっているんです。
先ほど局長は、子供の医療費の制度拡充について検討し、早急に結論を出すと答弁されました。ならば、近隣市町とのギャップを解消するために、本市独自の助成を直ちに行うことが、今、静岡市に住んでいる市民の子育て支援となり、温かい静岡市となり、人口流出を抑制する一助にもなります。そして、人口減少対策になるのではないでしょうか。
子ども医療費の助成は年齢の制限をつけているところもありますが、18歳まで通院費を無償にする予算は約5億円であり、本市の財政力を見れば可能と考えます。
そこで、お聞きします。
子ども医療費助成制度における通院費を18歳まで無償化する考えはないのか、お願いします。
◯こども未来局長(萩原祥古)
静岡市としては、先ほど答弁しましたとおり、子ども医療費の制度拡充等を検討する中で、対象とする年齢についても判断していきます。
◯杉本 護
ぜひ18歳まで入院も通院も無償、子育て世帯を応援していただきたい、早急に判断されることを期待をして質問を進めていきます。
次に、幼児教育・保育の第1子からの無償化についてです。
本市は、2023年4月から第2子以降の保育料の無償化を始めました。これは政令市では先駆けた取組となって、現在では7つの政令市で第2子以降無償化が実現をしています。子供を育てる上で大きな経済支援と言えますが、賃金が物価高騰に追いつかない今、さらなる経済支援が必要です。これがアンケートの結果でもあります。
瀬名地域で街頭演説をしていたら、乳幼児をだっこしていたお母さんが大きな拍手をくれました。話をすると、保育料第1子からの無償化をぜひやってください。収入の足しにとパートで働いていますが、保育料が月5万円を超えて、パート収入のほとんどが持っていかれて悲しくなってしまうと、こう言っていました。こうしたことは皆さんが感じたことではないでしょうか。
本市は第1子から無償にすると約10億円の予算が必要とされています。この10億円を単純に静岡市の予算から出すことだけを考えれば、市の負担が増えるだけですが、保育料の10億円が他の市民の新たな消費となれば、大きな経済効果をもたらすと思います。さらに、政令市初の子育て支援となってインパクトは大きく、子育て世帯からは、静岡市は子供を育てやすいまちだというふうに評価をされるのではないでしょうか。
こうして各自治体が保育料の無償化を始めていけば、国の施策として実現させる力にもなっていきます。
そこで、お聞きします。
全国の政令市に先駆けて保育料の第1子からの無償化を行う考えはないのか、お願いします。
◯こども未来局長(萩原祥古)
静岡市では、子供をもう一人持ちたいという市民の切実な声に応え、多子世帯の子育てに係る経済的負担を軽減するため、限られた財源の中で、令和5年度から第2子の保育料無償化を実施しています。
第1子を無償化するには、さらに毎年約10億円の財源が必要となり、恒久的な財源の確保は困難であるため、現時点では実施は考えていません。このため保育料無償化を全国一律の制度として実施するよう、国に要望していきます。
◯杉本 護
学校給食もそうなんですが、何かと国がやるべきこと、国に要望していく、こうした答弁がよくあります。今回もそうですが、考えてほしいのは、先ほど言ったアンケートにあるように静岡市民はまさに今、子育てへの経済的支援を求めています。本気で人口減少対策に取り組むのなら、静岡市から始めようということを提案したいと思います。そして、国を変えていこうではありませんか。改めて市独自の保育料第1子無償化を検討することを要望いたします。
次に、大項目の2の小規模修繕事業者登録制度について質問を移します。
先ほどの答弁で、一定程度の入札参加資格のない事業者にも仕事が回っていることが分かりました。
ちなみに、この登録制度を20年前から実施している広島市では、1件50万円以下の小規模修繕の2023年度の実績は、全体の工事件数は2,599件、金額は4億3,870万円余となっていて、そのうち入札参加資格のない登録業者の受注件数は483件で全体の18.6%、金額では1億3,070万円、29.8%となっています。
先ほど市が示した2023年度の実績では、入札参加資格のない事業者への発注は、件数で14%、金額で9%台です。本市と比べれば、登録制度がある広島市のほうが入札参加資格のない小規模な事業者の受注機会を増やしていることは明らかです。
さて、昨年の12月に民主商工会役員さんたちが市長と懇談をしました。要望は本市にも小規模修繕事業者登録制度をつくって、競争入札参加資格の名簿に登録されていない小規模事業者の受注機会を増やしてほしいとのことでした。市長も親身に耳を傾けていただき、小規模修繕事業者登録制度については研究してみると応じていただきました。
そこで、お聞きします。
この小規模事業者登録制度について、どのような研究をしてくれたのか、そしてその上で制度の創設についてはどのような課題があると考えているのか、お願いします。
◯財政局長(野村一正)
令和6年度に、政令指定都市の制度導入状況と静岡市の小規模修繕の発注状況調査を実施しました。政令指定都市の小規模修繕事業者登録制度の導入状況は20市中7市で、対象工種は内装、塗装、電気設備など13種から15種、1件の金額100万円以下の修繕業務を対象にしている市が多いことを確認しました。
また、静岡市の小規模修繕の発注状況は、令和5年度の実績で全体の98%を市内中小企業に発注しており、業者を選定した理由は、過去に施工の実績がある、施工現場が近いや新築時の施工業者であり内容を熟知しているなど、品質の確保、迅速性、効率性を考慮した選定が行われていました。
次に、制度導入の主な課題は2つです。
1つ目は、静岡市が建設業の許可を受けていない事業者を対象に登録名簿を作成する場合、工事や修繕の実績は当該事業者の自己申告でしかなく、建設業法の許可を受けた登録業者のように第三者による実績を証明するものがないこと。
2つ目は、事業者の実態確認のため、登記事項証明書、納税証明書や財務諸表など各種書類の提出を求める必要があると考えることから、事業者に対し新たな手間や労力、費用などの負担を課さなければならないことです。
◯杉本 護
まずは、民商静岡さんとの約束どおり、調査もし、研究もしていただきました。ありがとうございます。
そして、課題として、今、業務の履行能力と事業者への負担の2点を述べられたと思います。日本共産党静岡市議団も、この制度を学ぶために広島市に視察に行ってきました。広島市の場合は、この制度を小規模修繕契約希望者登録制度としていますが、まず競争入札参加資格名簿と同時に登録はできません。つまり、競争入札に参加するような一定規模の建設業者とは明確に区分され、ほとんどが小規模な事業者が登録されています。
また、ここに登録された事業者への発注高ですが、今までは修繕工事1件50万円以下だったんですが、物価高騰の折、今年度から100万円以下に拡大したとのことです。発注する際は、随意契約で2社以上から見積りを取り、1社完結で下請に回してはいけないルールとなっています。また、この制度を運営する予算は、市として特段に計上していないと言っていました。
また、登録すれば黙っていても仕事が来るわけではなく、仕事を取れるかどうかはその後のその事業者の営業努力が必要とも言っていました。
入札参加資格のない事業者に発注する際、工事の品質に心配がないかお聞きしたところ、特に気にしていないし、問題も生じていない。多少の不具合はすぐに直してもらっている。少額な工事なのでリスクも少ないと言っていました。
市が課題とした業務の履行能力については、広島市の20年間の経験から、それほど心配することはないように感じています。
さらに、入札参加資格のない事業者が登録し、市の仕事を請け負うのですから、過去に行った修繕業務の実績を示すなど一定の事務負担は必要とも思います。当局も調査研究しているわけで、分かっているとは思いますが、広島市は3年ごとに更新していて、登録業者が大勢いる広島民商にお聞きしたところ、登録申請はさほど面倒な内容でもないとのことでした。広島市では、現在172の建設業者が登録をしています。広島市が20年にわたって実施している事業であり、見るべき実績もあります。
さらに、今、インボイス制度の導入で一人親方のような零細業者も課税業者となって、消費税の納入が利益を圧迫しています。中小建設業者の仕事確保として、これまで以上の支援も必要と考えます。
そこで、お聞きします。
本市の小規模修繕事業者登録制度を始めるべきと考えますが、市の考えはどうか、お願いします。
◯財政局長(野村一正)
静岡市が発注する小規模修繕において、市内中小企業への受注確保は地域経済の活性化という観点からも重要であると考えます。
現在、小規模修繕業務においては、建設工事の入札参加資格を求めるなどの制限を求めておらず、既に広く受注が可能な状態となっております。加えて、発注各課に対しては、修繕業務の規模や特性を勘案した上で、広く市内中小企業を活用するよう周知しております。
このことから小規模修繕事業者登録制度の導入は考えておりませんが、引き続き現在の制度を活用し、市内中小企業の受注機会の確保に努めてまいります。
◯杉本 護
最後に、今の小規模修繕の関係なんですが、どこでもそうですが、結局、大きな現場でも最終的な現場を施工しているのは小さな業者なんです。やっぱりそこをしっかりと育成していかないと、今後の静岡市の様々な問題が、大きな生活面も含めて影響があると考えています。そういう意味では、この問題にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
以上です。