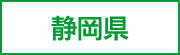◯寺尾 昭
発議第5号生活保護基準の引上げを求める意見書の提案者4人を代表いたしまして、提案理由説明を行います。
国は、物価高騰対策として、2023年度から2024年度は特例加算で一人月額1,000円加算、2025年度からは2年間を期限にさらに500円加算され、月額1,500円の加算となりますが、物価高騰に到底及ぶものではなく、対象も全生活保護世帯の58%にすぎません。政府は、1950年に現行の生活保護法制定以来、生活保護基準を2003年度に0.9%、2004年度に0.2%引下げ、2013年度から2015年度にかけては平均6.5%、最大10%の大幅引下げを行っております。その結果、総額670億円の減額となり、生活保護受給世帯の96%が影響を受けております。
最高裁判所は、2025年6月27日、国が2013年度から2015年度にかけて行った生活保護基準の引下げに対して、生活保護法に違反するとの判決を下しました。厚生労働省が行った保護基準引下げで、物価下落率を使ったデフレ調整には合理性がなく、厚生労働大臣の判断の過程、手続には過誤、欠落があり、生活保護法違反としたものです。これまでも、生活保護基準の引下げは違法と全国各地で訴訟が起こされ、地裁・高裁段階では違法との判決が多く出されていますが、これらへの統一判断にもなったわけです。
物価高騰が国民の生活を直撃しております。食料品をはじめとする2025年4月における全国の消費者物価は総合指数で前年同月比3.6%上昇となっているが、米をはじめとする食料品はこれをはるかに超えており、値上げはあらゆる生活必需品、電気、ガス、ガソリンなど枚挙にいとまがありません。とりわけ生活保護利用者にとっては、影響は深刻です。
生活保護法は、憲法第25条に基づく健康で文化的な最低限度の生活を保障するものとされておりますが、生活保護基準は生活保護法制定当時から低い基準であり、もともと余裕はありません。物価の高騰は直ちに生活に跳ね返り、関係者からはその改善を求める声が上がっています。実は私のところにも、多くの利用者から、こんなに物価が上がって、生活はいろいろ工夫しているけれども、もはや限界だ。何とか引上げてほしい、こういう切実な声も届いております。生活保護基準は、最低賃金制度や就学援助など国民生活に密接した様々な制度の基準となるいわゆるナショナルミニマムであり、その改善の意義は大きいといえます。今や生活保護により生活を営む方々を放置することは、このたびの最高裁判決の趣旨からも許されないのではないでしょうか。国におかれては、早急に物価上昇分に見合う改善と、併せて憲法がうたう健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護基準に引上げることを強く要請いたします。
議場における議員の皆さんの賛成をお願いいたしまして、提案理由説明といたします。