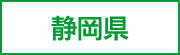◯(鈴木明美)
日本共産党の鈴木明美です。通告に従い質問します。
大項目、保健福祉センターの統廃合について質問します。
今年1月に出された保健福祉センターの再編及びこども家庭センターの機能強化(案)についてのパブリックコメントでは、母子保健と児童福祉の連携強化を賛同する意見以上に、これまで身近にあったものがなくなることへの不安の声、小さな子供を連れて健診へ出かける際の負担感など、距離が遠くなることへの意見が多く出されていました。身近にあるからこそ気軽に出かけられ、相談できるという、市民にとって安心感があるものです。今回の提案は、効率化だけを優先した統廃合と言わざるを得ません。
また、私は議員になる前、精神科訪問看護師として、保健福祉センターや児童相談所、生活支援課、子育て支援課、地域包括支援センター、障害福祉サービスなど、様々な市や外部の関係者とつながりを持つ利用者さんを支援してきました。そのため、そこでの経験から感じていたことを含め、今回の提案を掘り下げてみたいと思います。
中項目1、今回の提案に至る経過とパブリックコメントについてです。
今回、保健福祉センターの統廃合については、現場の保健師からの意見によるものとされています。
そこで、1つ目の質問です。
統廃合の提案に至るまでの経緯と、方針決定にどのように至ったのでしょうか。
次に、パブリックコメントでは、物理的な距離が遠くなることへの不安、反対の意見が多く見られました。特に、車を持たない家庭や高齢者にとって、地域によってはバスの乗換えも必要となり、バス代等の経費も負担となります。そして、保健福祉センターまで、より時間がかかるという時間的負担もあります。乳幼児健診のために小さい子供を連れて出かけることは、周囲への気遣いも必要となります。
わざわざ遠いところまで行かなくてはならないという心理的負担も含め、こうした負担感は、庁舎、もしくは、3か所に統合された保健福祉センターに行こうという、行動の動機づけへのマイナスの要因ともなります。
特に、状態が不安定な妊娠初期の妊婦さんにとって、母子健康手帳の交付のために、多くの市民が来庁し、混雑している庁舎へ出かけることの精神的、身体的負担は大きいものがあります。
乳幼児健診においても、複数回、健診日を設けるとしていますが、現在の保健福祉センターを利用された方からも、健診に行ったら混んでいて、相談したかったことがあったが時間切れとなってしまい、相談できなかったという御意見もいただいています。
集約することで、ゆとりのない健診の雰囲気を感じ取り、保護者によっては、本当はこの機会に相談したかったが、しにくかったと感じさせる、相談を諦めさせるということも起こり得るのではないでしょうか。
また、保健師が積極的に訪問を行うとされていますが、訪問活動を行う際、庁舎からでは移動の時間が増えることにより、1日に訪問できる箇所が減り、1回の訪問時間が十分確保できるのかという懸念などもあります。市民にとっては、回答欄に書かれた、御不便をおかけしますの一言で済まされるような負担ではないと言えます。
そこで、2つ目の質問です。
統廃合によって生まれる距離の課題について、市はどのように考えますか。
さらに、パブリックコメントの資料には、現状の課題として、自ら支援を受けることに消極的な家庭など、潜在的な要支援者へのフォローが不十分と書かれていますが、母子保健と児童福祉の対象以外にも、8050問題や高齢者の単身生活者、ひきこもりの方を抱える家庭など、様々なケースと問題があります。
多様な問題を抱える潜在的な要支援者については、まずは早期に発見し、支援につなげるまでが困難を要すると考えます。
そこで、3つ目の質問です。
潜在的な要支援者をどのように発見し、相談、支援につなげていくのでしょうか。
以上、1回目の質問です。
◯保健福祉長寿局長(山本哲生)
保健福祉センターの統廃合に係る3点の御質問にお答えします。
まず、統廃合の提案に至るまでの経緯と、方針決定にどのように至ったかについてですが、今回の取組は、保健福祉センターの統廃合ではなく、市民サービスの向上を目的として、保健と福祉のサービスの提供体制を改善しようとするものです。これは、現場の保健師の切実な声を基に検討を進めたものです。
近年、9つの保健福祉センターでは、窓口相談など、利用者は大きく減少し、一方で、保健と福祉が複雑に絡む困難な事例への対応が増えています。しかし、現在のセンターは少人数体制で、福祉職も常駐していないため、組織としての経験値が足りておらず、こうした事案に十分に対応できないことが課題となっていました。
このため、現場の保健師から、経験を積んだ保健師の知見を共有できる体制を、もっと福祉と連携できる体制を、という強い要望が上がり、協議を重ねた結果、保健師を区役所に集約し、福祉職と連携して支援できる体制を整えることとしました。
次に、統廃合によって生まれる距離の課題について、市はどう考えるかについてですが、保健福祉センターを9か所から3か所に減らし、保健師を区役所に集約することで、保健福祉センターの利用者や担当地区へ出向く保健師の双方にとって距離の課題が生じることを認識しています。
この課題に対しては、利用者の皆様の利便性の向上と職員のスケールメリットを最大限に生かすことで対応していきます。
まず、利用者の皆様の利便性の向上に係る対応については、例えば乳幼児健診において、保護者の方がより受診しやすくなるよう工夫を行います。これまで1~2か月に1回だった健診実施日を、今後は月に複数回へと増やし、受診日を選べるようにします。また、健診を実施する3つの保健福祉センターには、十分な駐車スペースを確保し、アクセス面でも利便性を高めます。
次に、職員のスケールメリットを最大限に生かす対応については、保健師を区役所に集約し、人的資源を効率的に活用できるようにします。これにより、家庭訪問や健康教室など地域へ出向く活動については、移動距離が延びる場合もあるものの、集約によるスケールメリットを生かし、これまで以上に地域へ出かける機会を増やします。
最後に、潜在的な要支援者をどのように発見し、相談、支援につなげるかについてですが、保健師を3か所に集約することで、これまで9つの保健福祉センターでそれぞれ行っていた事業の企画立案や事務作業などに要していた時間が削減できるようになることから、保健師がこれまで以上に地域に出向くことが可能となります。
これにより、地区の民生委員や地域包括支援センター、子育て支援センターなど、関係機関との情報交換の機会を増やすことで、顔の見える信頼関係を築き、潜在的な要支援者を把握し、相談支援につなげます。
◯鈴木明美
御答弁いただきました。
保健師さんたちの連携を強化し、迅速なサービスの提供体制を構築していきたいという思いは理解しますが、現状、限られた人員の中での苦しいやりくりでできた体制構築は、市民の立場から見れば、利便性や安心感が失われ、負担が増える提案と言わざるを得ません。
また、潜在的な要支援者の発見から、相談、支援につなげていくまでの過程においても、地域の様々な機関との連携なくしては、早期の発見につなげていくことができない現状であり、地域との連携が今後、ますます重要性を帯びてくると考えます。
次に、中項目2、保健福祉センターとこども家庭センターについて伺います。
今回の再編案では、保健福祉センターとこども家庭センターとのワンストップサービスが再編のメイン課題と認識しています。
そこで、質問です。
令和6年度において、母子健康手帳の交付件数の実績は何件でしたでしょうか。また、そこからこども家庭センターへとつなげた件数は何件だったでしょうか。
次に、こども家庭センターについてお聞きします。
厚生労働省が令和6年に出したこども家庭センターガイドラインによると、地域の関係機関との連携の推進及び支援体制の構築に際し、顔の見える関係性・信頼関係を築き、日常的な情報共有の円滑化が支援の協力体制の構築に重要としています。
私自身も精神科訪問看護に携わっていたときの経験をお話ししますと、ケース会議などを通じて顔の見える関係性を築けていると、お互いの役割も認識でき、ちょっと気になることでも早めに他の機関にも情報を共有したほうがよいのかなどの判断にも役立ちます。
逆に、関係性が薄いと、利用者さんの全体像を見て総合的に支援の構築をマネジメントするのが誰なのかよく分からないケースもありました。そのため、問題が生じると訪問看護ステーションの中だけで情報共有し、自分たちだけで解決しなくてはならない問題なのかも含め検討し、他の機関への相談、連携へとつなげることに対してタイムロスが生じていました。
また、他の機関や市の相談機関の支援の方針が変わった際も、細かな情報が共有されないと、利用者さんから方針変更等についての不満や不安の訴えがあったとき、的確で統一的な対応が不十分となります。そのため、様々な機関の支援者との連携の重要性は、直接、支援者へも影響を与えるものとなります。
そこで、質問です。
こども家庭センターでは、情報共有や支援をどのように行っているのでしょうか。
以上、2回目の質問です。
◯保健福祉長寿局長(山本哲生)
令和6年度において、母子健康手帳の交付件数と、こども家庭センターへつなげた件数についてですが、令和6年度の母子健康手帳の交付件数は3,491件です。
このうち、こども家庭センターへつなげた件数は563件となっています。これは、保健福祉センターとこども家庭センターで、情報の共有や支援方針の決定を行う合同ケース会議で協議した件数となります。
◯こども未来局長(萩原祥古)
こども家庭センターは情報共有や支援をどのように行っているのかについてですが、こども家庭センターは、妊娠期から子育て期まで、様々な困難を抱えるケースへの相談支援において、保健福祉センターや福祉事務所、療育施設などの外部機関と連携しています。
保健福祉センターとは、経済的に困窮している妊婦など、福祉と母子保健の一体的支援が必要なケースに対し、同行訪問や情報共有をしています。
また、例えば養育に不安がある保護者に対し、こども園への入園手続を手伝うなど、福祉事務所や外部機関と連携した支援を行っています。
特に、妊娠期から早期に支援することが重要であるため、こども家庭センターは、保健福祉センターと毎月1回、合同ケース会議を開催しています。そこでは、母子健康手帳発行時の面談で経済面や精神面で子育てにリスクがあると判断した妊婦に対する支援方針や、関係機関の役割分担などについて協議しています。
協議の結果、保健福祉センターとこども家庭センターが一体的に支援する必要があると判断した場合は、その妊婦に対する支援方針を両センターで共有し、継続的な支援を行うためのサポートプランを作成しています。令和6年度は、協議した563件中123件についてプランを作成し、これに基づき支援しています。
今後も、保健福祉センターや福祉事務所、外部機関と連携し、妊婦や子育て世帯に対し、切れ目のない支援をしていきます。
◯(鈴木明美)
先ほど答弁のありました母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんに対して、約16.1%の方がこども家庭センターと連携したケース会議につながる対象になるとのことで、この方々にとっては支援をより早期に受けられることにつながり、よいことと思います。
しかし、その他の約83.9%の妊婦さんにとっては、より身近にあった保健福祉センターではなく、遠い区役所まで行かなくてはならない負担感を強いられるということです。
保健師さんたちにとって、母子保健と児童福祉の連携強化、困難事例が増えていることへの改善の策として提案された今回の案ですが、果たして最善の策と言えるのでしょうか。
庁舎の中で母子保健と児童福祉の顔の見える連携は、統廃合によって強化されますが、支援の対象家庭に直接支援を行っていく外部の機関との連携について考えますと、これまでもお互い忙しい業務の隙間を縫っての連携であり、ケースによっては連携が不十分と感じることもある中、地域にいなくなることで、市民の皆さんと同じように地域の機関も気軽に情報共有、連携することがしにくくなるように感じます。
様々な困難を抱えている家庭が増加し、市としても重層的支援体制整備事業を進めようとしている中、より一層、支援者に対する情報を多角的に収集し、支援の構築をマネジメントしたり、支援の評価、再構築をするのが保健師や福祉職の役割だと思いますが、直接支援を行っている外部の機関とも顔の見える連携がより重要となります。情報の収集、共有のためには、日頃から地域の中に積極的に出ていくことが必要と考えます。
また、地域と積極的に連携していくことにより、潜在的支援者も早期に発見でき、小まめに訪問することで信頼関係を構築できるのではないでしょうか。
また、ひきこもりの方を抱える家庭などでは、家に訪問して話を聞いてもらう、電話相談することも困難なケースもあります。
まず、家族が安心して、いつでも相談できるようにするためにも、地域に保健福祉センターがあることのほうが大事であると考えます。現在、相談利用している方も同様と思います。また、保健師さんたちも、支援者に問題が生じたときなど、迅速に地域に出ていくことができるのではないでしょうか。
さらに、保健師の役割は、母子保健や困難家庭、高齢者対応だけではなく、コロナのような大規模な感染症への対応や、大規模災害時、避難場所での公衆衛生に関わる支援など保健師の専門性がより必要とされる場面があります。
コロナのときは、保健師さんたちは人員不足から、休む暇もなく、仕事をされていたと認識しています。そして、災害時は、日頃から地域に保健福祉センターがあり、そこを拠点として、保健師と地域住民が顔の見える関係性を構築できていることにより、住民の安心感にもつながると考えます。
もともと人員が足りず、幅広い役割を担う保健師の人材育成も困難な状況を考えれば、人員の充足がまず優先すべき点ではないでしょうか。
また、子育て支援を充実させるための今回の提案であるならば、不安を招くような、保健福祉センターを統廃合するのではなく、人員を増員し、こども家庭センターを保健福祉センターの中に併設する、もしくはICTの活用により、保健福祉センターからすぐこども家庭センターにつながる、福祉職とつながるようにすることのほうが、市民の……。