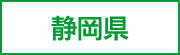◯寺尾 昭
年長者の寺尾 昭でございます。
この間、付き合う方がどうしても高齢者の皆さんが多いものですから、様々な声を寄せていただきました。そういう声に基づきまして、今日は高齢者の皆さんの代弁をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
特に今日は、高齢者の元気な活動を後押しするというテーマで発言したいと思います。
少子高齢化が進んでいるということ、人口減少をどう食い止めていくかと、今の議会の中でも議論がされておりますけれども、総務省統計局による2023年10月1日現在の年齢別推計人口では、65歳以上が約3,622万人で、総人口の29.1%、約3割ということであります。その中でも、75歳以上が2,007万人、これが16.1%となっているということであります。
一方、日常生活に制限のない期間、いわゆる健康寿命は、2022年の厚労省の調査では、男性が、案外短いなと思うんですけれども、72.57歳、女性は75.45歳だということであります。
ちなみに、皆さんも御承知だと思うんですけれども、静岡県の健康寿命は日本一ということでありますから、これは喜ばしいことだと思っております。
この平均寿命と健康寿命との差、つまり健康寿命と言えない期間がどのくらいあるかと言いますと、男性で8.49年、女性で11.63年、つまり健康寿命から亡くなるまで結構な期間があるということなんですね。
健康寿命を引き上げること、言い換えれば、元気に毎日を過ごすことができる期間を少しでも延ばしていくことは高齢者の生きがい対策と、また、医療や介護、福祉、そういう費用の縮減にもつながっていくということになるわけであります。
高齢者対策は、医療、介護、福祉と様々な分野がありますけれども、今日は、先ほど申しましたように、健康寿命をさらに引き上げるために応援し、元気に活動ができるように後押ししていきたいというテーマで発言いたします。
積極的に外に出て、様々な活動に参加している高齢者、例えば、自治会や自主防災会、地区社会福祉協議会、そのほか様々な役割を担い頑張っている方は、私の知っている方もたくさんいるわけであります。
とはいえ、一般的にはどうしてもお年を取ってくると、いわゆる出不精ということになっていくわけであります。気軽に外に出て活動できる場はどうしても必要だと、保障していかなければいけないわけであります。ボランティア活動に参加したくても、その方法が分からないという方もいらっしゃいます。
そこで、まず質問の第1は、高齢者の居場所づくりということがよく言われます。この居場所づくりについて、静岡市としてはどのように取り組んでいこうとしているのか、まずお伺いいたします。
先ほども話が出ましたけれども、本年度当初予算では、敬老祝い金の廃止など敬老事業の見直しが行われました。私の付き合っている今年80歳になる方がいるんですけれども、どうして私の年からなのか、非常に期待していたんですけどねと、こういう言葉も聞かれるわけであります。
敬老事業予算の全体の額としても、実は前年度と比較して減額となっております。もしかして、敬老事業は予算の削減が目的ではないかというような声も聞かないことはないです。
また、全てではないと思うんですが、敬老祝い金の廃止の理由の1つに、自治会の役員がこれを配っているため、大変な負担になっているというようなことがこの理由になっているということもあったんですが、支給の方法は幾らでもあるんですね。口座振替というような方法は今、非常に発達しておりますから、あまり理由にならないのではないかと思います。
いずれにしても、社会に貢献してきた方々への敬意を表することが必要じゃないかと思います。
そこで質問ですけれども、敬老事業の見直しの効果と今後の方向性についてどのように考えているのか、お伺いいたします。
高速道路や幹線道路での逆走、通園・通学の子供たちの列に車が飛び込むというようなことが、よくニュースになっております。年齢を重ねるごとに身体の機能が低下することは、誰にでもあることです。運転しなくてもいいんだったら、やりたくないという気持ちも率直に聞かれるわけであります。
しかし、運転免許証の返納となりますと、一挙に行動範囲が狭くなるということが悩みになる。それがこの返納を渋らせる、遅らせる原因にもなっているわけです。したがって、これはやっぱり個人の責任だけでは解決しないと言わざるを得ません。
そこで質問でありますけれども、外出機会を増やすため、運転免許証返納者への対応策と、公共交通機関の交通費の補助制度、こういうものを創設していく必要があると思いますが、その点、どんなふうに考えているのかお伺いして、1回目といたします。
◯保健福祉長寿局長(山本哲生)
高齢者の生きがい対策に係る3点の御質問にお答えします。
まず、高齢者の居場所づくりについてどのように取り組んでいくのかについてですが、静岡市はこれまで、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの場などを提供するため、施設においては老人福祉センターや老人憩の家等を整備し、活動においては、社会奉仕活動など地域を基盤に活動している老人クラブ等への経費の支援を生きがい対策として行ってきました。
そのほか、自治会館等で介護予防を目的に、地域ボランティアによって運営しているS型デイサービス事業、高齢者による介護施設等での地域貢献活動、元気いきいき!シニアサポーター事業、地域の集会場等で住民が主体となって介護予防に取り組む、しぞ~かでん伝体操など、地域とともに共創しながら、様々な活動を通じた高齢者の居場所づくりに取り組んでいます。
こうした中、高齢者の増加や健康寿命の延伸などにより高齢者のニーズは多様化しており、それに応えるため、これまでの延長線上にはとどまらない新たな取組が必要と考えています。
そこで、利用が高齢者に限定されている老人福祉センターで、年齢を問わず、幅広い世代も利用できる日を毎月設定し、高齢者が他の世代とともに時間を過ごす機会を提供することとしました。
この取組では、例えば、子供に将棋を教えたり、ニュースポーツを一緒に楽しむなど、世代を超えた交流が生まれ、子供たちから元気をもらえた、今後も参加したいなど、前向きな意見を多くいただいています。
今後も、高齢者施設において、多様な世代が交流する機会を提供するなど、高齢者の新たな居場所づくりに取り組んでいきます。
次に、敬老事業の見直しの効果と今後の方向性についてどのように考えているのかについてですが、敬老事業の見直しについては、個人への給付よりも地域全体で長寿をお祝いすることを市が下支えし、地域コミュニティの醸成を図ることが重要であるとの考えから、令和7年度から敬老祝い金、祝い品を廃止し、敬老行事を行うための補助金を拡充いたしました。
見直しの効果については、令和7年度に開催される敬老事業について、開催件数、参加人数、催し物の内容や参加された方の実際の感想など、敬老行事を実施した自治会等関係団体から聞き取るなどして検証を行います。
また、その検証結果を踏まえ、自治会等関係団体と十分に意見交換を行った上で、今後の在り方等について検討していきます。
最後に、外出機会を増やすために、運転免許証返納者への対応策と、公共交通機関の交通費補助制度を創設する考えはあるのかについてですが、静岡市では2006年度まで70歳以上の全ての方に対し、年間3,000円分のことぶき乗車券の交付事業を実施してきましたが、公共交通機関を利用する人だけが恩恵を受けるという課題があったため、他の高齢者の生きがい対策などの事業に転換した経緯があります。
また、外出機会を増やすために、運転免許証返納者へ助成する等の対応策を講じた場合は、運転免許証返納者だけが直接的な恩恵を受けることになります。交通弱者と言われる高齢者や運転免許証返納者等の対応策については、市内公共交通全体の利便性を維持・向上する中で検討してまいります。
◯寺尾 昭
意見・要望はまた後で言いますが、現役世代の美術館、博物館、スポーツ施設などの公共施設の利用は、日曜日、休日、夜間などに集中せざるを得ないわけであります。その点、高齢者は平日でも利用が可能であり、この世代の利用促進は社会参加を進める上でも、健康増進の点からも、さらに推進する必要があると思います。施設の効率的・効果的な運用にもつながるということであります。
その方策の1つが、入場料、利用料の割引という制度があります。ただ、多くの公共施設で、高齢者への入場料、利用料の割引を行っておりますが、無料のところ、3割程度、半額、全く割引はないというように、様々なんですね。その内容は一律ではありません。本市の施設も調べましたら、やはり同様となっております。
そこで質問ですが、高齢者の公共施設利用を促進するため、どのような取組を行っているのか、お伺いいたします。
次に、難聴高齢者の関係ですが、補聴器購入費助成制度については、これまでも本会議で、我が党の市川 正前議員なども質問してきました。御承知のとおり、昨年度からは、試行という形で進められております。これは、一歩、道が開いたという点では評価していきたいと思うんです。
補聴器と一口で言っても、種類、機能、価格はまさに様々。全ての音を増幅する、いわゆる拡声器型というようなもの、これは雑音も入ってしまうわけですけれども、必要な音域だけを拡大する型など、機能的といいましょうか、非常に様々な型があります。イヤホン型、はめ込み型、耳の裏に置く型もあります。
ところが、この価格が極めて広範囲なんですね。通信販売、テレビでやっているのを見ると、9,800円なんていうのがあるんですけれども、もう数万円、数十万円と価格も非常に様々であります。本市の助成額3万円では、とても足りないというのが率直なところではないかと思います。これはやっぱり、現在の補聴器購入の問題を制度化していく必要があります。
そこで質問ですが、難聴高齢者への補聴器購入費補助制度を創設すべきではないかと思っておりますが、これについてお答えください。
次に、清水区三保にあるグラウンドゴルフ場は、多くの愛好者──高齢者がもちろん多いわけですけれども、が利用してきました。しかし、このグラウンドゴルフ場は、水が非常に溜まってしまうだとか、あとは関連する施設があまりよくないということで、いろんな要望が大変出ているわけであります。
今回の補正予算で出ておりますように、同じ三保の区域内でありますけれども、また別のところにグラウンドゴルフ場を造ることになったということで、市長も御努力いただいたということだと思いますけれども、大変迅速な手続を評価したいと思うんですね。
ただ、高齢者も様々なスポーツをやっております。テニスもやる、卓球もやる、グラウンドゴルフももちろんやるわけですけれども、やっぱり高齢者の皆さんが使える施設をもっと拡充していくこと。
さらに、もう1つ、利用料の問題もあります。利用されている方々からは、もっと安くできないかというようなことも言われております。施設拡充、利用料の低減についても、併せてお聞きしておきたいと思います。
以上、2回目です。
◯保健福祉長寿局長(山本哲生)
高齢者の生きがい対策に係る2点の御質問にお答えします。
まず、高齢者の公共施設利用を促進するための取組についてですが、静岡市では2012年に作成した公の施設に関する使用料の設定基準に基づき、市内居住の70歳以上の高齢者に対し、生きがいづくり、社会参加の促進を図るため、過度の負担とならないよう配慮した料金を設定することとしております。
こうした施設は、静岡市美術館や歴史博物館など、市内に8か所あり、市ホームページで紹介するとともに、周知を兼ね、窓口で提示するだけで年齢確認することなく入場できるシルバーカードの交付も行っています。
一方、静岡市には、旧エンバーソン住宅、中勘助文学記念館など、年齢を問わず、全部または一部を無料で利用できる公共施設がありますが、これまで高齢者の社会参加の促進を図る目的で、対象施設を一覧にして紹介することは行っていませんでした。
そこで、新たに、年齢を問わず、全部または一部を無料で利用できる公共施設の情報を種別ごと一覧にし、ホームページで紹介するなど、高齢者の元気な活動を後押ししていきます。
次に、難聴高齢者への補聴器購入費補助制度を創設する考えはあるのかについてですが、高齢者本人が自身の聞こえに関心を持ち、難聴の疑いがある場合には、進行遅延のために早期の治療を受けることが大切です。
そのため、静岡市では、高齢者を対象に聞こえの確認の会に参加していただき、聞こえのチェック等を受けていただくことで、自身の聞こえに対する関心を高め、難聴の疑いがある場合には医療機関への受診を勧め、受診の結果、補聴器が必要と医師の判断を受けた方に、補聴器購入費用を助成する難聴高齢者早期発見・支援事業を行っています。
この事業は、難聴を早期に発見し、適切な医療を受けることで認知症予防や介護予防が期待できると考え、早期発見から補聴器購入費用の助成までを一体として行っています。
一方、国において、2018年から3か年計画で、聴覚障害の補正による認知機能低下の予防効果を検証するための研究を実施しました。このため、国に対し、その結果を早期に取りまとめ、医学的エビデンスを踏まえた上で、認知症予防の効果が認められる場合には、補聴器購入に対する全国一律の公的補助制度を創設するよう、大都市民生主管局長会議等を通じて要望しています。
このことから、静岡市が単独で補聴器購入費用を助成する補助制度の創設は考えておりません。
◯観光交流文化局長(岩田智穂)
グラウンドゴルフ場などのスポーツ施設拡充と利用料の低減について、市はどのように考えているかですが、まず、グラウンドゴルフ場については、市内で最も利用者の多い三保真崎グラウンドゴルフ場が津波浸水想定区域内にあり、大潮や雨の影響で利用できない日が多いことから、これらの課題を解消できる旧清水三保市営住宅跡地に移転し、管理棟やトイレなど施設を充実させます。
また、スポーツ施設全般については。新しい施設を整備するのではなく、既存施設を最大限に活用していきたいと考えています。
施設は特定の利用者や競技に特化したものではなく、様々な競技や年齢層の方々が多目的に利用できるものであることを周知し、既存施設の活用を促していきます。
次に、高齢者の施設利用料の低減についてですが、スポーツ施設の維持管理のためには、ある程度の受益者負担が必要であると考えます。現在、70歳以上の方を対象に、高齢者料金を導入しており、貸切りの利用の場合は一般料金の約7割、個人利用の場合は約5割に減額し、高齢者の負担を軽減することで利用を促進しています。
スポーツは、体力の維持・向上だけでなく、仲間との交流や心の健康にも大きな効果をもたらし、高齢者の生きがいの創出に寄与します。高齢者の方々を含む、誰もが利用しやすく、楽しむことのできるスポーツ施設の環境整備を進め、様々なスポーツを楽しむ機会の拡大につなげていきたいと考えています。
◯寺尾 昭
評価してもいい回答と、そうでない回答もありました。
3回目は意見・要望でございます。
高齢者の居場所づくりについても、様々やってきているということでありますので、今後、ぜひ地域包括ケアシステムの実現を目指すというようなこともあると思いますので、そういう形で進めていっていただきたいと思います。
敬老事業の関係です。敬老祝い金の廃止ということで、今後、また様々な分野の意見を聞いて検討していくというお答えでしたけれども、本当は祝い金を廃止したときに代わりにこうやろうということを同時に示していただくというのが順序じゃないかと。まず、外しておいて、後から考えるというのは、これはやっぱり後手後手というふうに言われても仕方がないのではないかと思いますので、ぜひ至急、検討していただきたい。
運転免許証返納者への対応です。これは、県内の幾つかの自治体はもう既にやっているんですね。多くの自治体が自治体独自でやっております。そういう意味では、本市は遅れている状況にあります。
補聴器購入の問題についても、認知症予防にも大きく貢献しますので、これもぜひ至急、検討していっていただきたいという要望を申し上げまして、質問といたします。